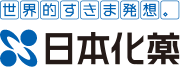データの利活用を通じて経理情報を分析し、
これまで以上に組織を支える基盤づくりに貢献する。
田中 誠人
MASATO TANAKA
経理部 会計担当
経済学部 経済学科|2016年卒
データの利活用を通じて経理情報を分析し、 これまで以上に組織を支える基盤づくりに貢献する。
田中 誠人
MASATO TANAKA
経理部 会計担当
経済学部 経済学科|2016年卒
- TOP
- 社員インタビュー
日本化薬に入社を決めた理由を
教えてください
大学では経済学部に在籍し、会計学や簿記論を学びました。その中で、会計士や税理士を目指したいと考える時期もありましたが、最終的には事業会社で経理に携わりたいと思うようになりました。就職にあたっては、営業職など幅広い職を検討しましたが、やはり大学で学んだことを活かしたいという思いから、経理を担当できる事務総合職を目指しました。私は特に、原価計算やコスト管理が求められる工業簿記に興味を持ち、製造業の経理に関心を抱くようになりました。日本化薬との出会いは、事務総合職の募集を採用サイトで知ったことがきっかけです。日本化薬の多岐にわたる事業展開や安定した収益基盤に魅力を感じ、幅広い事業環境で経理としての専門性を磨けると思い、入社を決めました。

現在の仕事・向き合っている
プロジェクトについて
入社後、カヤク・ジャパン株式会社の厚狭工場に出向し、約3年間、工場経理を経験しました。カヤク・ジャパンの厚狭工場は産業用火薬を製造する工場で、経理業務以外にも多くの経験をすることができました。その後、日本化薬本社の経理部に異動し、日本化薬単体の原価・損益計算業務を担当、月次・四半期・年次決算などに携わりました。現在は連結管理会計業務を担当し、グループ全体の原価・損益計算業務などを行っています。その他、BI(Business Intelligence)ツールを使ったデータ分析にも挑戦し、複数のダッシュボードを作成して決算結果の分析を行っています。2年ほど前から携わってきたERP・BI更改プロジェクトが今年の初めに完了し、現在は、稼働後に生まれた課題の抽出や対応にもあたっています。

心に残っているプロジェクトや
達成感を感じた仕事について
本社経理部で携わったERP・BI更改プロジェクトです。経理を代表する立場でプロジェクトに参画しました。厚狭工場時代や本社経理部でシステム周りのサポートをしていた経験から、プロジェクトメンバーに抜擢されたのだと思います。当初は予定通りの期間でスムーズに更改できるだろうと安易に考えていましたが、想像以上に多くの課題に直面し、気づけば当初の更改予定を延期せざるを得ないほどの長期にわたるプロジェクトになりました。基幹システムということもあり、自分の判断の誤りが大きな影響を与えてしまうという、責任感をひしひしと感じる仕事でした。その分、多くの知見と経験を得られたと思います。課題を解決するために、多くの時間を費やしとても大変でしたが、プロジェクトメンバーと協力しながら乗り越えた経験は、良き思い出であり、今後のキャリアにも役立つと思っています。

仕事における面白さややりがいを
教えてください
財務数値情報を正確に把握し、経営判断に必要なデータを提供することが、私たち経理担当者の役割です。経理担当者として数字を通じて課題を発見し、現状や解決策を模索することで、事業成長に貢献できる瞬間が一番やりがいを感じる時です。また、データを活用した分析業務など、経営判断を支える役割にも、経理業務の面白さと魅力を感じています。経理は数字を扱う仕事として地味な定型業務が多いと思われがちですが、近年では業務の複雑化・高度化に伴い、データ分析や業務効率化が求められるようになっています。その中で、ITの活用は欠かせないものとなり、経理とITの関係はこれまで以上に密接になっています。日本化薬においてもDX化が大きな課題の一つになっています。経理部でもIT関連業務に関わる機会が多くあり、データを効率的に利活用するために、BIツールでダッシュボードを作成し、これまで以上に数値の可視化や分析に時間が割けるように取り組んでいます。その意味でも、経理の役割は大きくなりつつあります。私自身、IT関連の資格取得を通じてデータ活用の知識を深め、より価値のある経理業務に貢献していきたいと思っています。
あなたにとって
世界的すきま発想。とは
“世界的すきま発想。”には、気づきの力で変革を起こし、持続的な成長を支える基盤を構築しようという意思が込められていると思います。私自身、BIツールを使った分析に取り組んでいますが、小さな改善を積み重ねてデータ活用を進めていくことは、現場の気づきを大きな変化につなげる姿勢を後押しするという意味で、”すきま発想”につながることだと思っています。ERP・BI更改プロジェクトも、システム移行という大きなプロジェクトの中で、小さな改善を積み重ねていくもので、すきまに眠る可能性を引き出し、変革と成長を両立させるスローガンの実践例だったと思います。