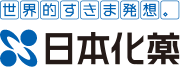TOP MESSAGE
変化に対して柔軟に向き合い
「世界的すきま発想。」で
新しいビジネスを生み出してほしい。
代表取締役社長
川村 茂之
SHIGEYUKI KAWAMURA

安全・安心、豊かさや感動を
キーワードとする製品群。
日本化薬は1916年の創立以来、100年を超える歴史を持つ会社です。日本最初の産業用火薬を製造する株式会社としてスタート、その後、基盤となる「火薬」「染料」「医薬」「樹脂」の保有技術を駆使し、これらを融合・変化させながら、時代のニーズに応える製品をつくってきました。近年はモビリティ&イメージング事業領域、ファインケミカルズ事業領域、ライフサイエンス事業領域の3事業領域を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。
日本化薬の製品は、人々の安全・安心、生活の豊かさや感動といったキーワードで表すことのできる製品群に使われています。例えば、自動車の安全装置、エアバッグやシートベルトのプリテンショナーは、命を守る製品に使われるものです。医薬品は健康に資する製品、インクや染料、半導体に使われる樹脂などは人々の生活を豊かにしていくために不可欠な製品となっています。また、日本化薬の製品は、他社があまり手掛けていないニッチな領域に強みを発揮していることが多いため、「その手があったか」といった驚きや感動をもたらしています。


海外売上比率が50%以上を占める
グローバルに活動する会社。
日本化薬は一つひとつのビジネスが必ずしも大きくない事業の集合体となっている点に特徴があります。このため、世界を席巻するようなビッグビジネスを手掛けているわけではありません。ただ、それゆえに意思決定が早く、小回りの利く会社になっています。
もともとは国内市場を主体とする会社でしたが、近年はグローバル化が進んでいて、海外売上比率が50%を超える会社です。従業員も海外のほうが多くなっています。製造拠点は中国をはじめとするアジアを中心に、世界へと広がっています。
日本化薬はグループのコーポレートスローガンとして「世界的すきま発想。」という言葉を掲げています。まだ誰も知らない価値の眠る場所をいち早く見つけ、独自技術で世界に必要とされる高付加価値な製品を提供し、ニッチ市場のグローバルNo.1を目指すという意気込みを示したフレーズです。社会や人々の暮らしは常に進化していますが、進化に伴って必ず「すきま」も生まれてきます。その「すきま」に私たちはビジネスチャンスを見出しているのです。

考えられる限りの手を尽くし
全力で取り組んだ先に見えてくるものがある。
少し私自身のことをお伝えしようと思います。新入社員として配属されたのは医薬事業で、MRとして19年を過ごしました。思い出深いことの一つに「サリグレン」という薬が発売された時のことがあります。この薬はシェーグレン症候群という難病に使う薬ですが、当社と大手製薬会社が同じ有効成分を持つ薬を同時に発売したため、激しい販売競争が繰り広げられました。とある大学病院を担当していた私は、考えられる限りのあらゆる努力をしました。大手製薬会社は人員も多く、さまざまな薬を扱っていますから、大学病院に対する影響力も日本化薬とは勝負にならないほど大きなものがあります。そんななかでこの競争に勝ったのは、大きな自信になりました。
その後、私はセイフティシステムズ事業の姫路工場に異動しました。この事業も19年担当しましたが、東南アジアに製造拠点を作ることになった時のことが印象に残っています。東南アジアのどの国がよいのか、国の特徴、税制、政治体制、気候などを調べ上げてマレーシアに決定しました。マレーシアの中でどの場所がよいのか、雇用状況、語学力、インフラの状況などを入念に調査し、場所を定めました。そして時間も限られていた中、多くの製品を生産する工場を予定通り立ち上げることができました。医薬事業、セイフティシステムズ事業と二つの事業での思い出について触れましたが、共通するのは、考えられる限りの手を尽くして、全力で取り組んだということ。そこで初めて見えてくるものがあるのです。


コミュニケーションを大切にして
出来ることは全部やる精神で挑戦しよう。
これから日本化薬のなかで活躍する若手社員に期待することは、大きく分けて二つあります。一つは遠慮なく積極的にコミュニケーションを取ってほしいということ。会話上手な人を求めているという意味ではなく、自分が疑問に思ったことを上司なり先輩なりに聞く姿勢を大切にしてほしいということです。もう一つは、自分が今関わっている仕事に全力で取り組むこと。先に私自身の体験に触れましたが、できることは全部やる、といった精神でぶつかっていってほしいと思います。
日本化薬の社風の特徴は、若い人の意見を積極的に取り込んでいくことです。私は社長として、そんな雰囲気をさらに加速していく空気を醸成したいと思っています。「世界的すきま発想。」をビジネスに活かすためには、研究者同士の横のつながりだったり、営業担当者が顧客から聞いた情報を社内にフィードバックしたりするといった形のコミュニケーションも大切です。そんな考え方や仕組みを今まで以上に整備していく考えです。
世界の政治経済情勢を見渡すと、激しい変化が起きています。一方、デジタル技術の進展は著しく、そのスピードにもついていかなければなりません。これから日本化薬で活躍したいと考える皆さんには、ぜひこのような変化に対して柔軟に取り組み、新しい技術やビジネスを生み出すために挑戦していただきたいと思います。志しを同じくする若い人たちと一緒に働くことを楽しみにしています。